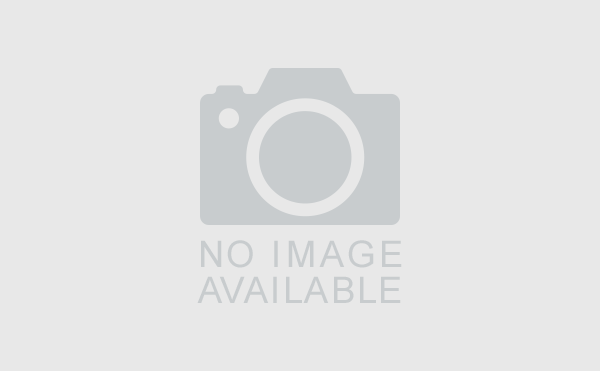Blog #8 Scientific EngagementはMSLの活動目的か手段か?
昨今MSLの生産性についての議論をよく耳にします。MSLはField Medicalと言われる通り、医療現場に一番近いところで活動するMedicalスタッフです。従って、売上を上げるためのプロモーション活動はできないというルールであることは間違いありません。一方で、多くの主に外資系企業のマネジメントは、MSLがビジネスにどのように貢献しているのか、どうしたらもっとビジネスに貢献していることを、売り上げやシェアといった、コマーシャルに関連する数字以外で、数値的に明確に示すことができるのか、その議論に多くの時間を割いているように思います。

そこで鍵となるのは、このScientific Engagementという言葉です。通常コマーシャル部門が使用するCustomer Engagementと対比して、Scientific Engagementと言ったときに、ある意味、MSLの人たちの、Reactiveな仕事に加えてのProactiveな仕事のあり方のイメージが、なんとなく共通理解でできるのではないでしょうか。
しかしながらScientific Engagementとは、具体的にどのような活動のことを言うのか、その達成度をどのように評価するのかを説明してください、と問うと、その答えはだんだん怪しいものになってきます。
なぜそうなるかというと、Scientific Engagementが達成された時の状態が明確に言語化できていないからに他なりません。このことを解決するために、会社によっては、Scientific LadderのようなBelief Stepsのモデルを準備して、MSLによる顧客評価を行なっている会社もあるようです。しかし、この方法の問題点は、MSLの主観的評価であることと、そもそもLadder定義の言語化があやしいことになっていたりするために、あくまでも参考資料としてしか活用されていないのが現状だと思われます。
つまり、MSLが訪問する医師一人ひとりそれぞれに対して、あなたの目指すScientific Engagementが成し遂げられた時に、医師の行動はどのように変わるのか?そして、その変化は、地域医療にどのようなポジティブな影響が起きるのか?その像が具体的に言語化できていないから、Scientific Engagementは、概念としては理解できるが、具体的にはよくわからない状態が続いているのだろうと思われます。
そう考えると、MSLの生産性、つまりビジネスへの貢献度の測定といった時に、このScientific Engagementが達成された状態を数値で目標として持っていて、その進捗が測定できるような仕組みになっていることが、各製薬企業のマネジメント層のフラストレーションを解決する唯一の方法なのでしょう。
先日MediNewの記事で、私とJMDCの小沢さんとの対談記事が掲載されました。今やBig Dataで処方箋ベースの薬物治療の変化が追えるようになってきました。その中には、Scientific Engagementの結果としての医師や患者さんの行動の変化を評価できるものがあります。例えば、診断率やそのイノベーティブな治療薬が含まれるクラス採用率、あるいは、専門医受診率などがそうです。
このように、新たな数字が手に入るようになったおかげで、Scientific Engagementの状態が、地域ごとに目にみえるようになってきたわけです。
さて、それでは、このScientific Engagementのレベルを向上させることはMSLの一つの活動目的なのでしょうか? それは違うと考えています。確かに、MSL活動目的の一つをScientific Engagementのレベル向上だとして、その数値で評価することはできると思いますが、大切なことは、あくまでも目的はその対象疾患で苦しんでいる患者さんの治療を最適化することに他なりません。Scientific Engagement評価でMSLの行動評価は可能になりますが、あくまでもそれは手段であり、本来の目的は地域医療の最適化であるということだと考えています。ここを履き違えるとせっかくのBig Dataの分析も本来の意味をなさないことになってしまいます。Big Dataの活用によるScientific Engagementの測定は、地域医療の最適化のための手段の一つとして、MSL活動推進の指標になるものと考えています。